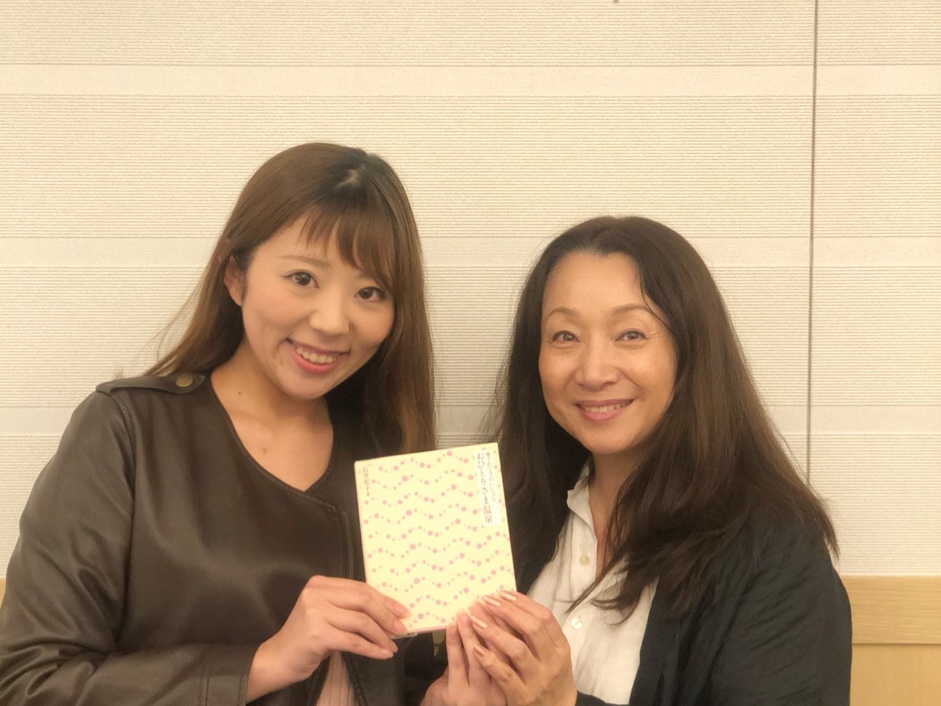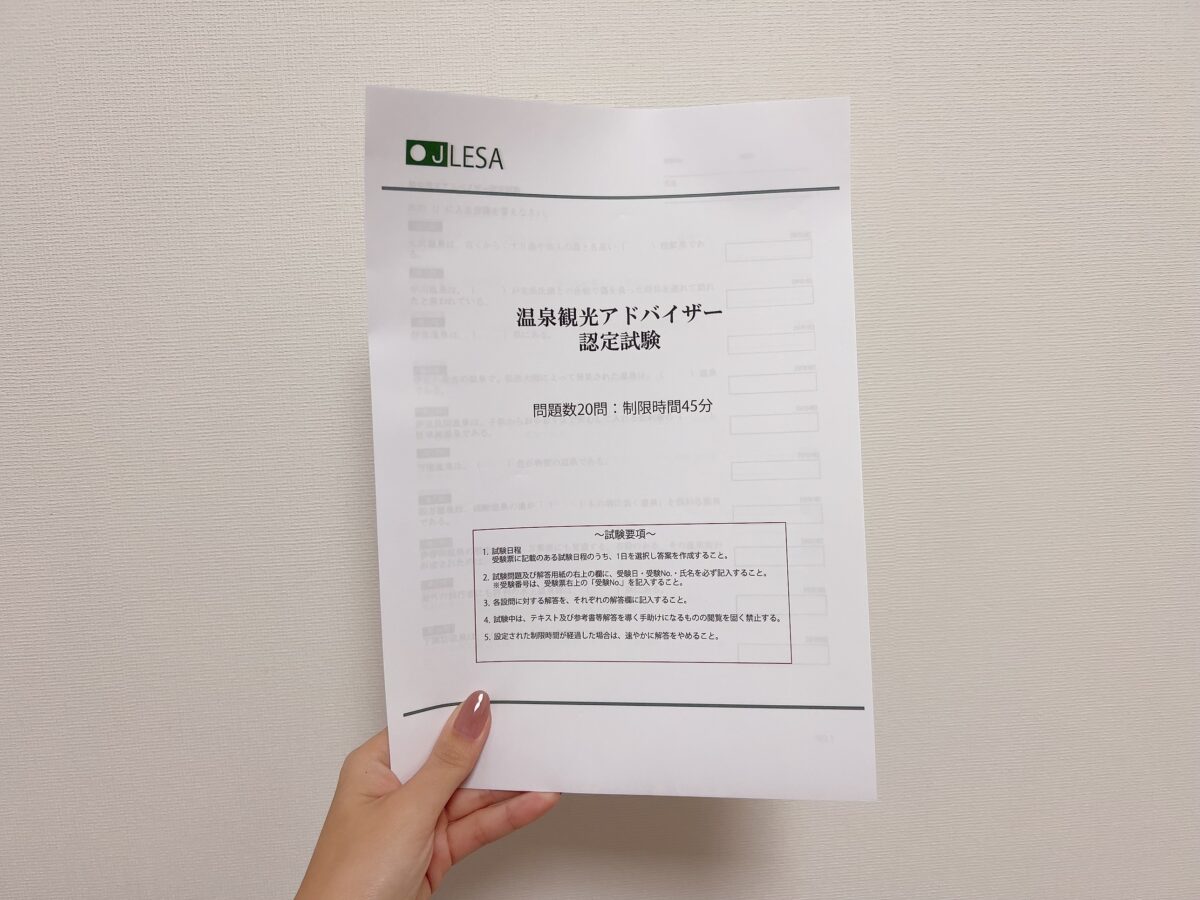【受験体験記】通訳案内士試験|歴史 試験対策や勉強法・勉強時間まとめ

こんにちは!温泉ソムリエeriです。
これまで私は「温泉ソムリエマスター」や「温泉観光士」など、温泉や観光に関する資格に挑戦してきました。
そして今年は、これまでの温泉や観光の経験をより役立てられるように、外国人観光客に日本各地を案内できる国家資格「全国通訳案内士試験」を受験してみました。
この試験は、日本の歴史・地理・一般常識・外国語の知識が問われる難関資格で、合格すると観光ガイドとして活動できるのが特徴です。
その中の「歴史科目」は100点満点中70点以上で合格ですが、私が去年の過去問を初めて解いたときはなんと28点…。中学・高校以来の日本史でゼロからのスタートでした。それでも半年間の学習で、本番では9割以上を取ることができました!
この記事では、歴史科目で合格点を取るために私が実際に取り組んだ勉強の流れ・使った教材・当日の試験の様子をまとめています。来年以降受験される方の参考になれば幸いです。
通訳案内士試験「歴史科目」の概要
通訳案内士試験の歴史科目は、日本の古代から現代までの政治や文化、外交まで幅広く出題される科目です。正直、範囲がとても広くて、私も最初は「全部覚えられるかな…」と不安でした。
問題は、四択のマークシート形式で、全部で30問。試験時間は30分なので、時間を意識しながら解く必要があります。
合格点は、70点(30問中21問以上正解)。ちょっとドキドキしますが、過去問を分析すると「文化史」「外交史」「近現代史」がよく出るので、効率よくポイントを押さえれば大丈夫です。
歴史科目の勉強時間の目安
私が最初に去年の過去問を解いたときは、なんと100点中28点でした…。中学・高校以来ほとんど日本史に触れていなかったので、「基礎からやり直さないとダメだ」と痛感しました。
そこから逆算して、合格点を狙うために全体でだいたい150時間を目標にして勉強を進めました。平日は1〜2時間、休日は少し多めに学習するペースで進めると、効率よく取り組めます。
勉強の進め方は、私の場合こんな順番でやりました。
- 通史をざっと理解する
→ 古代から現代までの流れをざっくり把握。 - 頻出分野を重点的に復習
→ 過去問でよく出る文化史・外交史・近現代史を中心に学習。 - 過去問でアウトプット
→ 時間を計って実践形式で解くことで、本番に強くなる。
最初は「無理かも…」と思うくらい点数が低かったですが、ポイントを絞って勉強することで、少しずつ得点が伸びていきました。こうして、基礎ゼロに近い状態でも、合格圏内に届く手応えをつかむことができたので、次のパートではわたしの勉強の流れを紹介します!
歴史科目の勉強の流れ(私の場合)
私が歴史科目の勉強を進めたのは、ざっくり言うと 3月から8月までの約6か月間。
中学・高校以来ほとんど日本史に触れていなかったので、最初は「覚えられるかな…」と不安でしたが、自分なりのペースと工夫で少しずつ点数を伸ばすことができました。
3月:過去問で現状把握&通史理解
まず去年の過去問を解いて、どれくらい自分の知識が抜けているか確認しました。結果は100点中28点…。基礎から学び直すために、まずはYouTubeで通史解説動画を見ながら、古代から現代までの大まかな流れをざっと理解しました。

おすすめは【高校日本史まとめ完全版】というYoutube動画です!とてもわかりやすくて半年間で何度も何度も試聴しました!
4月:ドラマと漫画で感覚的に理解
通史を終えたら、今度は時代ごとに漫画で細かい出来事を確認して、対応する過去問を解く方法を取り入れました。
例えば
- 飛鳥時代の漫画を読む
- 過去問で飛鳥時代の問題を解く
この方法は、文字だけで覚えるよりも頭に入りやすくておすすめです。

わたしのおすすめは「講談社 学習まんが 日本の歴史」!何度も読んで流れを把握しました!
あとは、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を見て、鎌倉時代の政治や人物の流れを感覚的に覚えました。
5月〜6月:近現代史の理解&暗記開始
ゴールデンウィーク明けから「30日完成 スピードマスター日本史問題集」を使って重要事項の整理と暗記をスタート。少しずつですが、点数を伸ばす手応えが出てきました。
大河ドラマ「西郷どん」を見て、幕末〜明治〜近現代の流れを感覚的に覚えました。
7月〜8月:過去問中心の実践学習
過去5年分の過去問に取り組み始め、問題を解く感覚を身につけました。「スピードマスター」で弱点を復習しながら、得点の安定を目指しました。この時期になると、「あ、この時代はこういう問題が出やすいな」と感覚で分かるようになり、自信もついてきました。
歴史科目で使ったおすすめ参考書・教材
歴史科目の勉強で私が実際に使った教材は、知識を身につけるインプット と 覚えたことを確認・定着させるアウトプット に分けて取り組みました。両方を組み合わせることで、効率よく理解を深められます。
インプットに使った教材は4種類
文章だけで暗記するのは大変なので、動画や漫画で歴史の流れを視覚的に掴むのがおすすめです。私はドラマ鑑賞が大好きなので、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」や「西郷どん」を、歴史の勉強だと思わず普通に楽しく見ていただけで、重要な人物や出来事を感覚的に覚えることができました。
漫画も組み合わせると、問題に出たときに「あ、この話だ!」とすぐ思い出せるので効率的です。もちろん基礎知識の確認には教科書や図録、全体の流れを把握するにはYouTubeも活用しました。視覚的なインプットを中心にすると、理解がスムーズに進みます。
YouTube動画
わたしのおすすめは【高校日本史まとめ完全版】です。最初に通史をざっと理解するのに便利。映像で流れを把握できるので、頭に入りやすいです。
漫画
わたしは「講談社 学習まんが 日本の歴史」の全20巻を読破しました。時代ごとの出来事を感覚的に覚えるのに最適。過去問で問われる部分とリンクさせやすいです。
大河ドラマ
わたしは「鎌倉殿の13人」と「西郷どん」を試聴しました。人物や事件の背景をイメージで理解できます。視覚的に覚えられるので、暗記が楽になりました。
諸説 日本史図録
歴史を幅広くカバーするなら 「諸説日本史図録」 がとても便利でした。写真や図表が多く、視覚的に覚えられるのが魅力。時代ごとの流れや重要人物、事件などが整理されていて、基礎知識の復習や整理の中心として重宝しました。
アウトプットに使った教材は3種類
過去問(過去5年分)
これはもう必須です。最初は点数が低くても、過去問を繰り返すことで「よく出るテーマ」「覚えやすい問題」が分かってきます。私も最初は100点中28点でしたが、過去問を繰り返すことで、少しずつ点数が伸びていきました。過去問は、日本政府観光局(JNTO)のサイトから入手することができます。
スピードマスター日本史
重要事項の整理と暗記に便利な1冊です。薄くて持ち運びもしやすく、短時間でも効率よく学習できます。私は大河ドラマや漫画で感覚的に覚えた知識を、この本で整理して頭に定着させました。とはいえ、今年の試験問題を振り返ると、スピマだけでカバーできる範囲は約40%。この本だけでは十分とは言えないので、他教材と組み合わせて学習することで、合格点を狙いやすくなります。
予備校の模試
実力を客観的に確認するために、予備校の模試も役立ちました。本番の雰囲気や時間配分の感覚を掴めるだけでなく、自分の弱点が明確になるのがありがたいポイントです。私は模試を受けることで、「ここは覚えられていないな」と感じた部分を集中して復習できました。わたしが利用した予備校は、CELとTrue Japan Schoolです。どちらも先生の解説授業がおもしろくておすすめです。
2025年度歴史科目の問題を振り返る
実際の試験問題を1問ずつ振り返ると、どの教材で対応できたかや、自分が覚えやすかった方法が見えてきます。来年以降受験する方の参考になるよう、私が取り組んだ方法や感想をまとめました。
今年の出題傾向は、昨年度の問題と同様、前半は地域ごとの問題、後半は江戸時代や近現代の問題が中心でした。今年の春から夏にかけて、私は「勉強旅行」と称して広島・岡山・岩手・日光を訪れたのですが、ちょうど今年の問題に出題されたのでラッキーでした。
(1)世界遺産「平泉」について

大問1では、世界遺産「平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―」について5問出題されました。
- 歴史的な問題:1083年に起きた清原氏の内紛に始まる戦乱の名称など
- 文化的な問題:中尊寺金色堂の工芸技法、毛越寺の庭園様式、松尾芭蕉の句
少し難易度の高い内容もありましたが、漫画や図録で基礎を確認していたので、なんとか思い出すことができました。

(2)世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」について
大問2では、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群―古代日本の墳墓群―」について6問出題されました。
- 仁徳天皇陵古墳の大きさ
- 古墳時代の埴輪について
- 古墳の名称
- 岩戸山古墳に埋葬される磐井
- 遣唐使に関する問題
漫画や図録で基礎を押さえていたので、細かい名称や数字も思い出しやすかったです。
(3)日本文化のひとつ、温泉について
大問3は、日本文化の形成に大きく影響を与えた温泉に関連する問題でした。出題内容は、歴史上の著名人とゆかりのある温泉や重要史跡に関するもので、直接温泉自体ではなく、温泉地にまつわる歴史が問われました。
- 函館市・湯の川温泉:アイヌの蜂起
- 秋田県・大湯温泉:縄文時代の遺跡
- 静岡県・熱海温泉:戦国大名
- 愛媛県・道後温泉:鎌倉新仏教
- 佐賀県・武雄温泉:朝鮮出兵の名称
この問題は過去問や問題集でも取り上げられることが多く、正答率は高めだったと思います。私は温泉関連の歴史を実際に訪れた経験と結びつけて覚えていたので、答えやすかったです。
(4)上野・日光東照宮について
大問4では、江戸時代の将軍徳川家の帰依を受けた僧「天海」について問われました。
- 寛永寺や日光東照宮にゆかりのある人物
直前に勉強旅行で日光東照宮を訪れ、天海の像を見たことが役立ちました。

(5)江戸時代の地方都市について
大問5では、江戸時代の地方都市に関する問題が出題されました。
- 岡山県・後楽園
- 北前航路
- 松江城
- 伊勢神宮
過去問や図録で地理的・歴史的背景を押さえていたので、思い出しやすかったです。

(6)幕末の薩摩藩について
大問6は幕末の薩摩藩(鹿児島県)に関する問題。
- 島津斉彬
- 尚古集成館
私の祖母が鹿児島に住んでいたこともあり、名前は耳にしていた上に、勉強中に大河ドラマ「西郷どん」を見ていたので、スムーズに答えられました。
(7)〜(10)明治時代以降について
大問7から10では、明治時代以降の地域や歴史が問われました。
- 北海道の開拓使
- 琉球処分の過程(沖縄の創設)
- 大阪市の都市整備事業
- 大日本帝国憲法発布
- 米騒動
近現代のテーマは過去問での頻出分野も多く、スピードマスターや図録で確認していた内容と重なる部分が多かったため、思い出しやすかったです。
9割取れたわたしが思う合格点を取るためのコツ
私の場合、効率よく合格点を狙うポイントは大きく分けて3つありました。
現地へ行く!
百聞は一見にしかずという言葉のとおり、何回テキストや問題集で暗記をしようとしても、自分の目で見たものには敵いません。
世界遺産を中心に実際に現場を訪れることで、歴史上の人物や出来事のイメージが頭に残りやすくなります。例えば、日光東照宮で天海の像を見たことや、平泉を訪れた経験は、試験での出題を思い出すきっかけになりました。特に今回使用していた市販の問題集では当日の問題がカバーしきれていない部分もあったので、行ける範囲で「現地へ行くこと」は特におすすめです。
楽しんで学べば暗記いらず!
2つ目は「暗記科目」だと思わずに、楽しむことです。学生時代は本当に日本史が苦手で、というのも暗記が大の苦手だったからなんです。でも今回大人になって日本史を学び直して、大河ドラマや漫画などでストーリーとして触れることで、自然と理解が進みました。
さらに、大河を見ていない時代については、自分の頭の中でドラマを作っていました。例えば「推古天皇」目線や「持統天皇」目線になって、その時代の主役を勝手に立てるんです。そうやって人物を主人公にして歴史を俯瞰すると、単なる出来事の羅列ではなく、一つの物語として記憶に残りやすくなりました。
文章だけで暗記するよりも、感覚的に理解できるのがポイントです。
アウトプットを繰り返し解く!
わたしは過去問とスピードマスターを試験当日までに、それぞれ5周ずつ取り組みました。何度も繰り返すことで、単語や人物、年代の記憶が定着し、問題に出会ったときに迷わず答えられる力につながりました。
この3つのポイントを意識するだけでも、効率よく合格点を狙えると思います。特に今回使用していた市販の問題集では当日の問題がカバーしきれていない部分もあったので、現地へ行くことは特におすすめです。
当日の試験会場の雰囲気
2025年度の一次試験は 8月17日(日)、東京都内を希望した受験者は 日本大学文理学部キャンパス で行われました。

私が到着してまず感じたのは、受験者の年齢層の高さです。30代中盤の私が最も若いのではと思うくらいで、50〜70代の方が多くいらっしゃいました。年齢層の幅が広いことに少し驚きつつも、大人になってもチャレンジする姿勢がかっこいいな と思いました。
| 外国語 | 11:00〜12:30(90分) |
| 休憩 | 12:30〜13:30 |
| 日本地理 | 13:40〜13:10(30分) |
| 日本歴史 | 14:40〜14:10(30分) |
| 一般常識 | 15:40〜16:00(20分) |
| 通訳案内の実務 | 16:30〜16:50(20分) |
当日のスケジュールは午前中に 英語科目、その後 1時間の休憩 を挟み、午後に 地理・歴史・一般常識・実務 の順で行われました。各科目は試験開始の15分前に着席。休憩時間は教室内の自席で軽く飲食ができ、免除科目がある方は校舎内のロビーで勉強している方が多かったです。
会場全体は落ち着いた雰囲気で、殺伐とした感じはなく、係の方も丁寧に案内してくれました。実際に試験が始まると、周囲の動きはあまり気にならず、問題に集中することができました。
私自身は、過去問や模試である程度時間配分を体に覚えさせていたので、「思ったよりスムーズに進められる」と感じました。終わった後はほっとすると同時に、やれることはやったという達成感がありました。
歴史科目に挑戦する方へ
全国通訳案内士試験の歴史科目は最初は覚えることが多くてハードルが高く感じますが、過去問やスピードマスター、ドラマ・漫画など、自分に合った方法でコツコツ取り組むことで着実に力がつきます。私も中学・高校以来ほとんど歴史に触れていませんでしたが、150時間を目安に勉強した結果、少しずつ点数が伸び、達成感を味わえました。
大人になってもチャレンジする楽しさは格別です。受験を考えている方も、自分なりの工夫やペースを見つけて進めば、必ず前に進めます。私の体験が少しでも参考になり、「やってみよう」と思ってもらえたらうれしいです。